上記の問いは、古典を読む場合に必ずつきまとう問題である。
古典読書に否定的な意見として以下の二つがある。
一つ目は
昔の本は難解であり読むのが難しい上に無駄に長い。そのため、現代の古典の解説書を読めば、簡潔に短時間で容易にその古典のエッセンスが理解できる。その方が経済的でいいではないか。
という意見である。
二つ目は、
昔の本はそもそも、その書籍が書かれた当時の人々や社会を中心にして記述されているので、現代には何の役にも立たない。現代の最新の書籍を読む方が有意義だと思う。
という考えである。
これらの否定的意見に対して、古典読書の適切な肯定的意見を行うことは意外と難しい。
というのも、読む人によって考え方が違うということも一つの要因として挙げられるが、主に古典を読むことは、古典に触れることによってでしか得られないものを理解するために行うことが多いからである。
例えば、形而上学のような哲学分野は、世界の根本(究極)原理を具体的事象を超えて考えることを主眼としているので、すぐに日常生活に役立つとは明確には言えない。
しかし、形而上学を知ることは、一つの考え方や観点を学んだり、批判的思考や論理的思考、そして、言葉の重みや深みを感じたりなど、「言葉で形容しがたいもの」を得ることができる。
この「言葉で形容しがたいもの」を本来の意味を歪めずに伝えるのは容易ではない。
そのため、このような「言葉で形容しがたいもの」が理解できない古典読書否定派に対して、古典読書肯定派は「古典は現在の我々にも役に立つ」というもっともらしいことを言って上記の二つの意見を逃れようとする。
そして、過去の有名な経営者が、古典を愛読していたことを例証しながら、「偉大な経営者が読んでいたし、古典の考え方を応用して成功を収めている」と言って古典を読まない人をなだめすかす。
あるいは、古典読書肯定派の中には、否定派の人を理解がない人と決めつけ、ある種の軽蔑のまなざしを向けて否定派をまともに相手にしないという方法を取る人もいる。
しかし、このようなやり方でよいのだろうか?
冒頭の問いに立ち返ってみると、この「なだめすかし」は、古典を古典として読む価値があると伝えずに、古典を俗物にまで落として正当化しているのにすぎないのではないか?
また、否定派を無視するというのは、古典読書の意義を正確に伝えるという説明責任を逃れているだけか、そもそも無批判に古典は良書だと決めつけて、本人自身もなぜ古典を読んでいるのかわからずにやり過ごしているだけではないのか?
そうすると、古典を読む意味とは何か。
なぜ古典をよむのか。
古典を読むからこそ、その意義を明確化する義務はあると考えられる。
私が考える古典読書の意義は、以下の4点ほどが挙げられる(以下の4点以外でも理由はたくさんあると思いますが、私の薄弱な思考では以下のものしか思いつかなかったので4点にさせていただきます)。
- 目次
- ①古典は現在直面している問題の解決に通じる一つの意見を提案している。
- ②現代を批判的に見る。現代を根本から考える。
- ③古典は問題を指摘した書籍であり、問題や思考法の発端となった書物である。
- ④自分の考えや発想が二番煎じではないかと気づく。自惚れないために。
スポンサーリンク
①古典は現在直面している問題の解決に通じる一つの意見を提案している。
この考え方は、「役に立つ」という「なだめすかし」に少し似ているが、①と似て非なるものである。
前者の考え方は、古典の内容と文脈を理解せずにただ有益そうな言葉を探してひけらかしたり、本来とは全く異なる意味で自分に都合の良い解釈をして納得することである。
他方、後者は、古典を本来の意味として受け止め、実際に直面している問題に応用することである。
もちろんここでは後者の意味であり、分かりやすい例の一つとして、デュルケームの『自殺論』が挙げられる。
世界のOECD加盟国の中でも自殺率が高いことで有名な日本で、参考になる書籍である。
特に、自殺類型の「アノミー的自殺」は日本でも実際に生じうる(生じた)出来事である。自殺のタイプが推測できれば、自殺対策の第一歩となりえる。
そのため、この例は古典が現代の問題解決につながることを示唆している。
|
スポンサーリンク
②現代を批判的に見る。現代を根本から考える。
古典を読むことは、現代への流れの大元を知ることでもある。
現代が別の姿ではなく「この現代」であるのも歴史があってのことである。
「そもそもどういう経緯で今の状態になったのか」「どういう論理が現在で働いているのか」それを記述するのが古典である。
一番わかりやすい例は宗教である。
特にキリスト教は、原理や神をどう解釈するか、キリスト教の制度がどのように考えられていたかが時代によって異なる。
過去から現代まで、これらの解釈の違いで殺戮や戦争が生じている。
宗教で見られるような問題を解決するには、宗教の理念や制度を知る必要があり、古典読解が欠かせない。
根本を知り各解釈や論理を見極めて批判的に考えることで、新しい答えを思いつくことができ、争いを未然に防ぐことも可能となる。
スポンサーリンク
③古典は問題を指摘した書籍であり、問題や思考法の発端となった書物である。
②と少し重なるが、現代の問題は過去に指摘された問題がそのまま続いていることが多い。
②での神の考え方はわかりやすい例として挙げられる。古典は問題の発端とその考察過程を我々に教えてくれるのである。
さらに、ニーチェの「系譜学」、ハイデガーの「解釈学」、そしてソシュールの「構造主義」などのように、古典で提唱されて現代でも実践されている思考法は数えるときりがない。
(現代の書籍で「系譜学」や「解釈学」の名前がついている書籍が膨大にある)。
これらの方法論は、古典を読むことでしか得られないもののひとつである。
|
|
|
スポンサーリンク
④自分の考えや発想が二番煎じではないかと気づく。自惚れないために。
古典を読めば、どんなことがこれまで行われてきてどんなことがまだ行われていないのかが正確にわかる。
「自分が初めてある考えを提唱した」と吹聴する傲慢な人間に限って古典を読まない(古典と全く同じことをしているのに気づいていない)。
古典を知る者は、過去に行われなかった新しい問題に着手することができ、時間をその問題に多く割り当てることができる。
このような人が増えると、現代の問題の解決も早まるし、今後生じうる問題の対策法も多く考えることができるようになる。
さらに、新しい考え方が次々と出てくるので、さらなる人類の発展も見込める。古典は発展を促すのである。
以上の4点は、古典を読む意義を明確に正当化する根拠であり、古典を読む意味の一側面だと考えられる。
スポンサーリンク
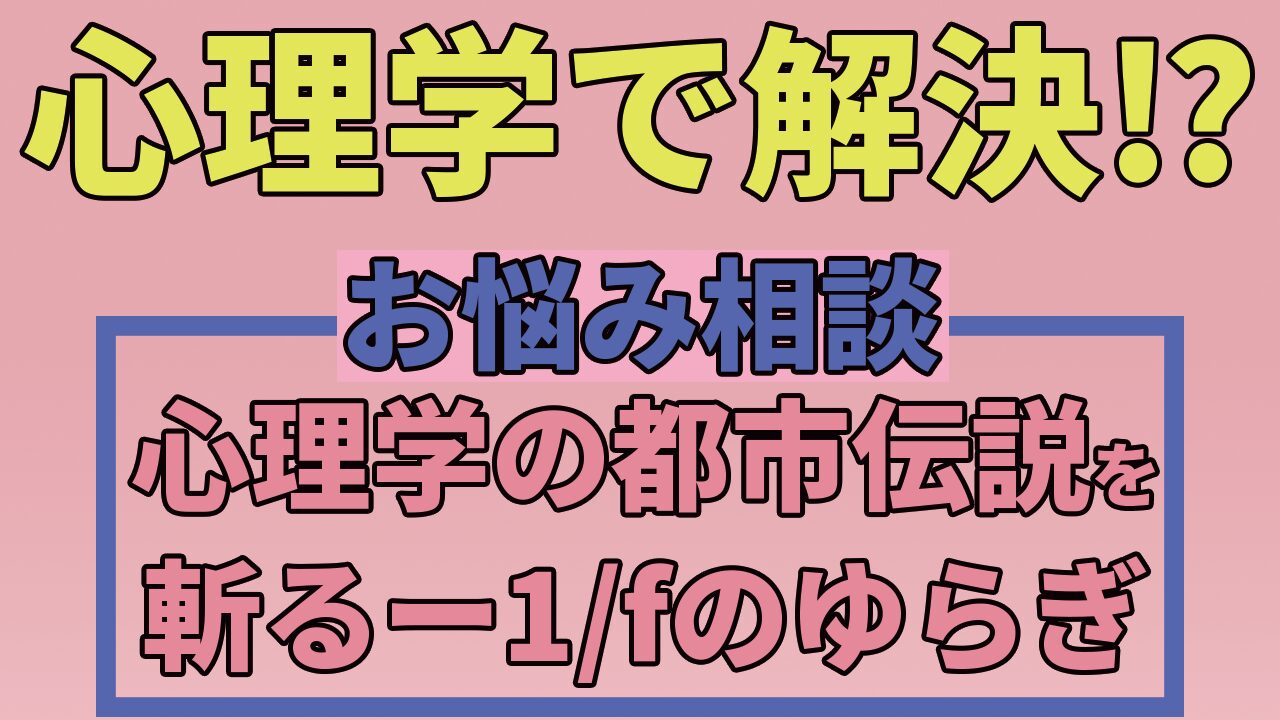
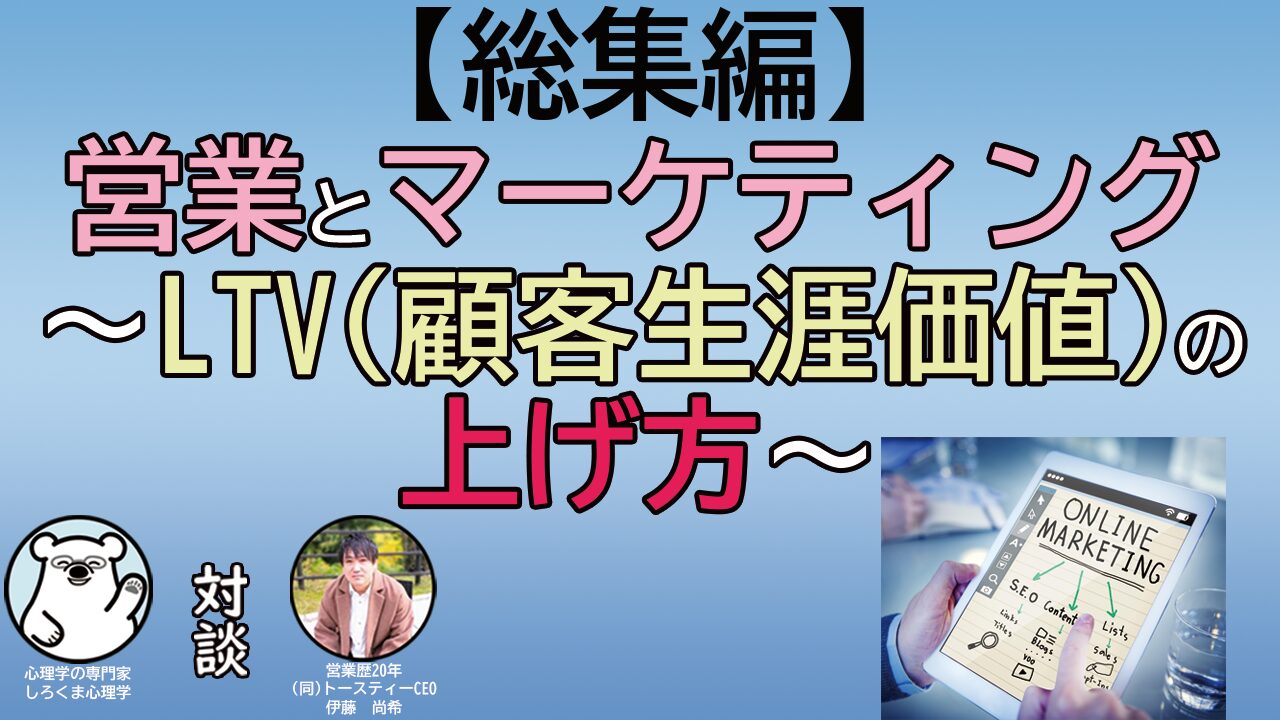
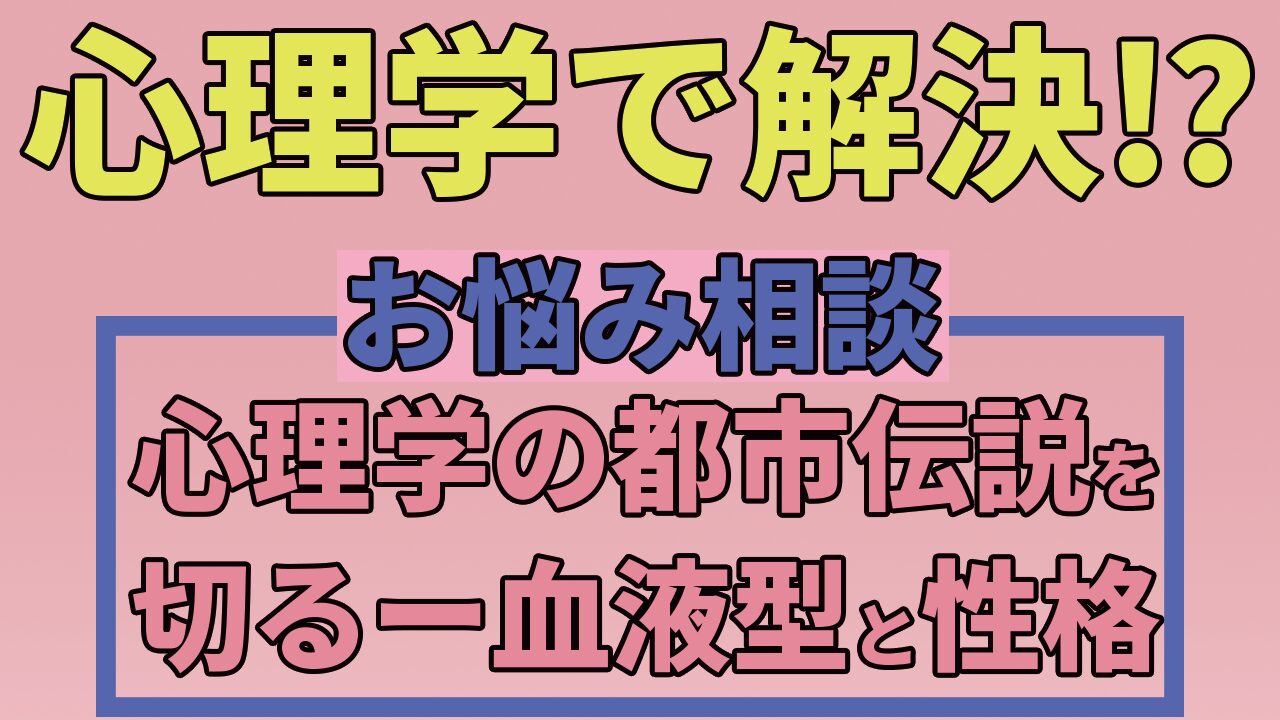
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/186d3a18.9a110ced.186d3a19.fb6d97a9/?me_id=1275488&item_id=12568793&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookoffonline%2Fcabinet%2F2390%2F0015580978l.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookoffonline%2Fcabinet%2F2390%2F0015580978l.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18319d8b.0051d57f.18319d8c.5f095036/?me_id=1213310&item_id=10096175&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0033%2F00336394.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0033%2F00336394.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1955f8a2.7ed13f9c.1955f8a4.a0f2b6f3/?me_id=1368547&item_id=10094373&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmottainaihonpo-omatome%2Fcabinet%2F06789208%2Fbkpjksplfp4k0doh.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmottainaihonpo-omatome%2Fcabinet%2F06789208%2Fbkpjksplfp4k0doh.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18319d8b.0051d57f.18319d8c.5f095036/?me_id=1213310&item_id=18134020&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8226%2F9784327378226.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8226%2F9784327378226.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)