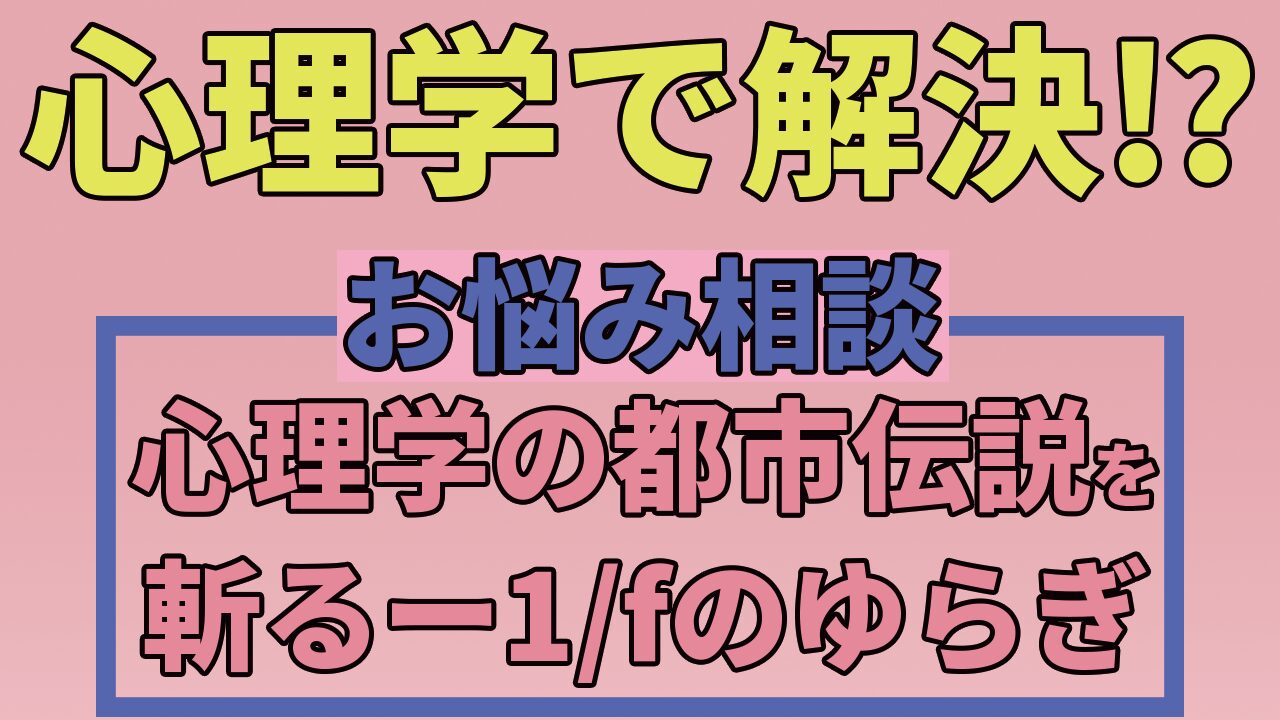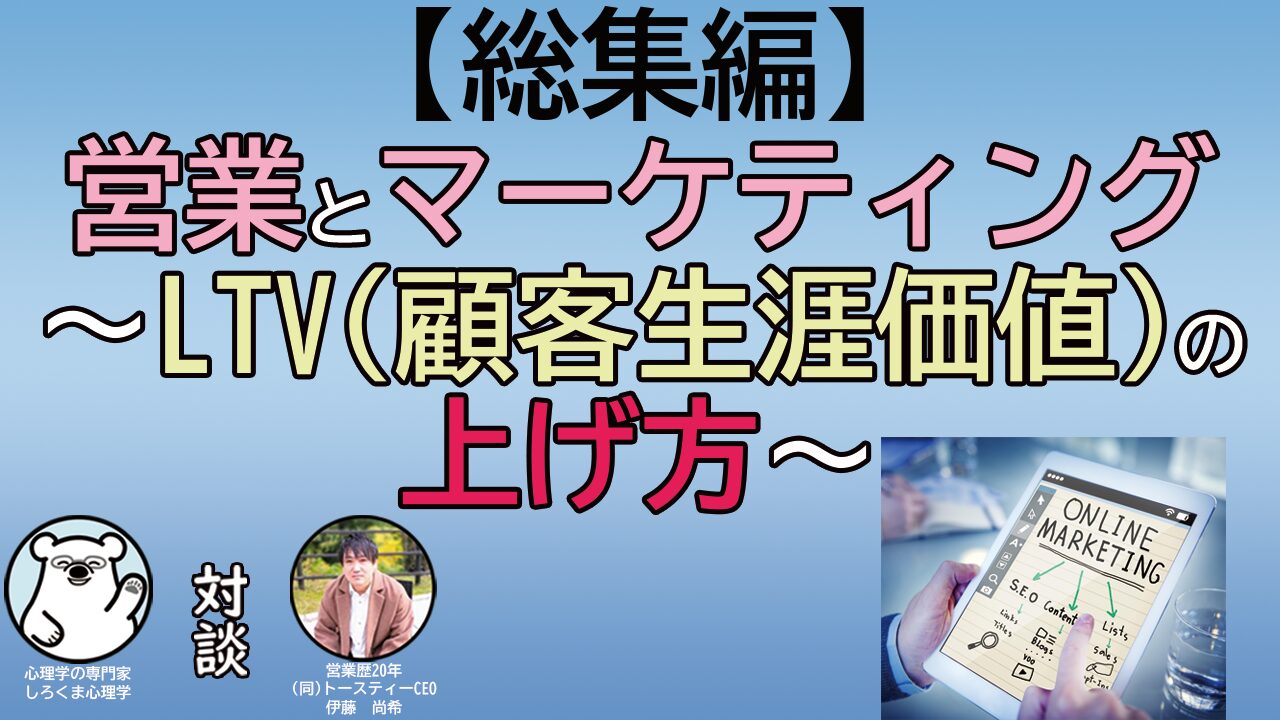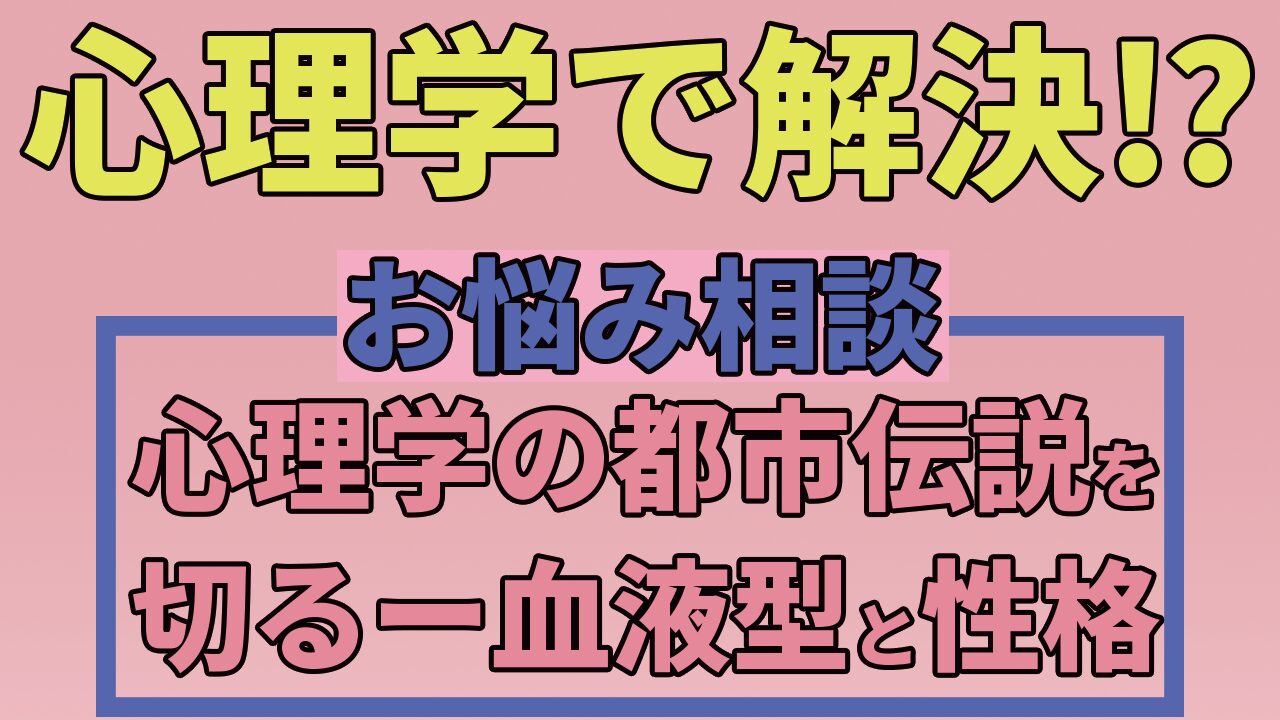・アイデンティティとは何ですか?
・目まぐるしく変化する社会にもうついていけません。
・会社に使われる時代は終わった。
・ありのままの自分でありたい。
現在このような悩みや思いを抱えている方は少なくありません。
以前は家族や会社ぐるみで行動を共にしていました。
しかし、現在はどうでしょうか?
家族で過ごす時間は少なくなり、飲みに誘われても行かない、地域のイベントには誰も来ない。
こうした集団や共同体の時代は過ぎ去ってしまいました。
そんな時代を先取りしていたのがジグムント・バウマン『リキッド・モダニティ』です。
バウマンは個人化社会を予期し、個人のアイデンティティが問題になると主張します。
今回の記事では、そんなバウマンの『リキッド・モダニティ』を題材にして、変わりゆく現代社会の問題点を洗い出します。
一方、会社や共同体が有していた権力も将来的には変わらざるを得ません。
バウマンの考察に加え、将来の権力論について考えたいと思います。
本記事では以下のことが学べます。

2. 近代社会の実像
3. 将来的な社会の姿と個人のあり方
4. アイデンティティの問題
5. 将来的な権力の姿
目次
①リキッド・モダニティ:固定されない変化し続ける近代社会の姿
スポンサーリンク
①リキッド・モダニティ:固定されない変化し続ける近代社会の姿
バウマンは、本書の題名にもありますように、近代社会を液状化した近代社会(リキッド・モダニティ)と呼びます。
では、リキッド・モダニティとはどのような社会なのでしょうか?
主に四つの特徴があると言います。
1) 秩序という制限からの解放
今日的状況は個人の選択の自由、行動の自由を制限すると疑われる手枷、足枷がことごとく溶かされた結果生まれたといえるだろう。秩序の硬直性は人間の自由が蓄積された結果であり産物である。
まず一つ目の特徴として、個人の自由が挙げられます。
これまで、自分の所属している地域や共同体などの秩序に縛られていました。
しかし、リキッド・モダニティではそうした秩序が消滅したのです。
よって、個人が自由に行動できる社会となります。
2) 個人と集団との絆の消失
流動的近代であるいま、坩堝に投げこまれ、溶かされかけているのは、集団的な事業や集団的な行動において、かつて、個人個人それぞれの選択を結んでいたつながりである―個人的生活と集団的政治行動をつなぐ関係と絆である。
二つ目の特徴が、個人と他人とのつながりや絆が喪失したことです。
秩序だけではありません。
集団という概念すらもう古いかのように、個人で完結している社会です。
集団的行動・集団的事業・つながり・絆。
そした他者との接点がなくなっていくのです。
そして、この状況をバウマンは以下のようにまとめてもいます。
あらかじめ貴族がきめられた「関係集団」の時代から、「全般的比較」の時期へ移行しつつある
集団というまとまりではなく、自分と他者との関係のみが存在する社会。
その社会では、自分と他者がどう違うのかという比較が前面に押し出されます。
スポンサーリンク
3) 世襲や伝統の解体
現在、近代的「溶解力」のいわば再配分、再分配がおこっている。溶解力の影響を最初に受けたのは、貴族だけによって決定される世襲財産のような伝統的制度、あるいは、行動の選択を制約しうる枠組みであった。
三つ目の特徴は、我々が先祖代々から受け継ぐような世襲的枠組みや伝統的枠組みの解体です。
以前の記事「頭でっかちの合理主義では政治は動かない!実践知を問う政治論」でマイケル・オークショットの保守主義思想をご紹介しました。
彼は、伝統や経験を大切にするという思想でした。
しかし、現代社会はもうそのような伝統や世襲など関係なくなったのです。
4) 責任は個人に帰結する
われわれの生きる近代は、同じ近代でも個人、私中心の近代であり、範型と形式をつくる重い任務は個人の双肩にかかり、つくるのに失敗した場合も、責任は個人だけに帰せられる。
それゆえ、最後の特徴として、全ての責任は個人に帰せられるという点です。
これまで共同体や集団で物事を進めていた時代では、責任は個人一人ではなく集団で取っていました。
しかし、現代では、共同体や集団がなくなった以上、全ては個人に尽きます。
スポンサーリンク
②近代で問われる個性とアイデンティティ
バウマンは近代社会の特徴を四つあげました。
そこで問題となるのが、近代における個性やアイデンティティだと言います。
近代のどんな時期においても、どんな社会においても、「個人化」は他律的にではなく、自律的に行われる。しかし、個人化の苦悩にはさまざまな違いがあり、世代によって、また、同じ世代でも、個人によってそれは多様である。
つまり、個人化は自分で行わなくてはいけません。
これまで共同体や地域が与えていた個人のアイデンティティのようなものを自分で作らないといけない苦悩に陥るのです。
九州出身だから義理堅いとか関西出身だからユーモアがあるといようなそういう個性が付与されず、自分で見出していくのです。
個人化や差異化の達成には、自分で個性を打ち出すことが必要です。
これは、自由と引き換えに個人に与えられる試練とでもいえるでしょう。
バウマン曰く、
世界の秩序を管理し、善悪の境界を監視していた最高司令部がみえなくなったいま、世界には可能性の無限の選択肢がある。
個人的には、この無限の選択肢の中でもがく人々の姿が浮かびます。
選択肢が決まっていたり少数であれば、ある意味楽です。
選ぶという行動には能動的な努力を必要とするからです。
それが無限にある状態は、自由の副作用と言えるでしょう。
そんな状態で、重要になってくるのが実例です。
権威が信奉者をつくるのか、信奉者が権威をつくるのかはおくとして、実例対権威の関係で、現在、より重要で、より必要とされているのは実例のほうである。
バウマンは、○○ブートキャンプに出てくるお兄さんやお姉さんのように、素敵な人生を歩んでいる人を実例の一つとして示しています。
こうした、無限の選択肢がある中で、個人がアイデンティティを得るのは、実際の成功例や具体的実例なのです。
個性化をどのようにすればいいのかわからない状態の個人にとっては、実例は一種の啓示のように見えるのです。
それゆえ、権威が理想化された実例の方へと向かいます。
この権威の話は最後にします。
バウマンは、こうした時代で必要とされる能力をあげています。
不安的なアイデンティティの原材料に、意図的にもろい材料が使用される世界においては、われわれはつねに臨機応変でなくてはならない。とにかく、柔軟性と、外的世界の変化にすばやく対処できる適応性を保持しておかねばならない。
バウマンは、めまぐるしく変化するリキッド・モダニティの世界では、アイデンティティすらも確固としたものではなく移り行くものとします。
それゆえ、必要なのはそうした社会や個人の変化に対応できる能力。
しかし、この現実はとてもしんどいです。
だからバウマンも次のように言っています。
アイデンティティの流動性と柔軟性は、自由の再分配の手段にはなっても、解放の媒介にはならない。それゆえ、流動性と柔軟性は祝福でもあり、呪いでもある―魅惑的で、待望される一方、忌避され、恐れられるといったふうに、人に矛盾した反応をひきおこす。それらは一貫性のない、なかば神経症的な感情を生みだす曖昧な価値である。
このように変動する社会の中では、自由な無限の選択肢はありますが、選択の重圧に押しつぶされます。
そして、自由を求めていたけれども、選択から逃れたい、選択するのがしんどいという恐れが生まれるのです。
そうしたアンビバレントな状況下に人間はいるのです。
スポンサーリンク
③それでもつながりを求めてもがく個人
バウマンは、現代が、常に変化する社会でアイデンティティすらも不安定な状況であることを指摘しました。
しかし、そんな中でも、個人は他者とのつながりを求めるというのです。
外では手にいれようとしても手にはいらない、帰属意識、共同体の一員たる実感のようなものを、殿堂の内側で、買い物客/消費者はみつけだそうとしているのかもしれない。
結局、「消費」空間にでかけることは、失われた、どこかよそにいってしまった共同体をさがす航海である。
バウマンは、買い物客の観察をします。
すると、買い物客は、自分と同じ物を買う他の買い物客や店員との接触というつながりを見出すというのです。
買い物をする間は、自分と同じような他者がいると感じられるのです。
人間は、個性化やアイデンティティの確立に必死でいながらも、他者とのつながりを求めてもがいているのです。
共同体は自力で生き残れず、構成員が自主的に、責任をもって支えていかねばならない―この意味で、あらゆる共同体はつくられた共同体であり、現実であるより計画、個人の選択のまえでなくあとで成立するものである。
しかし、そうして求めた他者とのつながりを感じられる共同体は以前とは別の姿となります。
その共同体は、生まれる前から元々あったものではなく、意図的に能動的に作られるものなのです。
自分でサークルを立ち上げたり、地域のコミュニティを作ったりということ。
人は、個性化に必死でありながらも、共同体を求める存在であることをバウマンは言いたいのだと思います。
共同体の重要性ですね。
実際に、バウマンは、『コミュニティ』という本も書いています。
スポンサーリンク
④まとめと権力論の変化
以上が、ジグムント・バウマン『リキッド・モダニティ』の概要になります。
まとめると以下のようになります。
- 現代のような近代社会は、秩序のような固定したものがなく、常に変転している。
- その社会の中では、個人は共同体や地域などに頼らずに自分でアイデンティティを形成しないといけない。
- しかし、個性化やアイデンティティ形成はとても負担が大きい
- 個性化やアイデンティティの時代でも、共同体を人間は求める。
共同体といっても、以前のようなものとは似て非なるものです。
地域や会社などの自然な集団的なコミュニティではなく、個人が自ら能動的に作り出して維持しないといけないコミュニティです。
そんな社会で問題となるのが権力論だと私は思います。
というのも、こうした集団やつながりが喪失した社会では、権力自体が成立しなくなり、権力のあり方も変わらざるを得ないからです。
バウマンも以下のように言っています。
現在は、たぶん、なによりもまず、ポスト・パノプティコン時代だといえる。パノプティコンで重要なのは、責任者が「その場所」に、近くの監視塔のなかにいなければならないことだった。・・・パノプティコンの終焉は、管理者と被管理者、資本と労働、指導者と支持者、戦争の敵味方のあいだの、相互関与の時代の終焉を予感させる。
つまり、権力を持つ誰かが他の人に仕事をさせるというような関係性はなくなりつつあるのです。
共同体や集団の力が薄まる以上、「上からの権力」は消滅しつつあります。
フリーランスやギグエコノミーの増加ということもあり、会社という形態もいつかは消滅するのかもしれません。
もしかしたら、仕事もプロジェクト型になって「必要とあれば集まる」くらいの感覚になっていく。
そうすると、個人は、複数の案件を持って仕事をする形態になる。
バウマン曰く、「アイデンティティが利益を生む」時代です。
この社会で権力や権威は必要となるのでしょうか?
政治などの場では必要となるかもしれませんが、ロバート・ダールや宮台真司が述べるような従来型の権力や権威はなくなるかもしれません。
もしかしたら、権力という言葉は「リーダーシップ」などの言葉に置き換わるかもしれません。
バウマンの言う「実例」による自分のすごさ自慢の時代へと移るのかもしれません。
スポンサーリンク