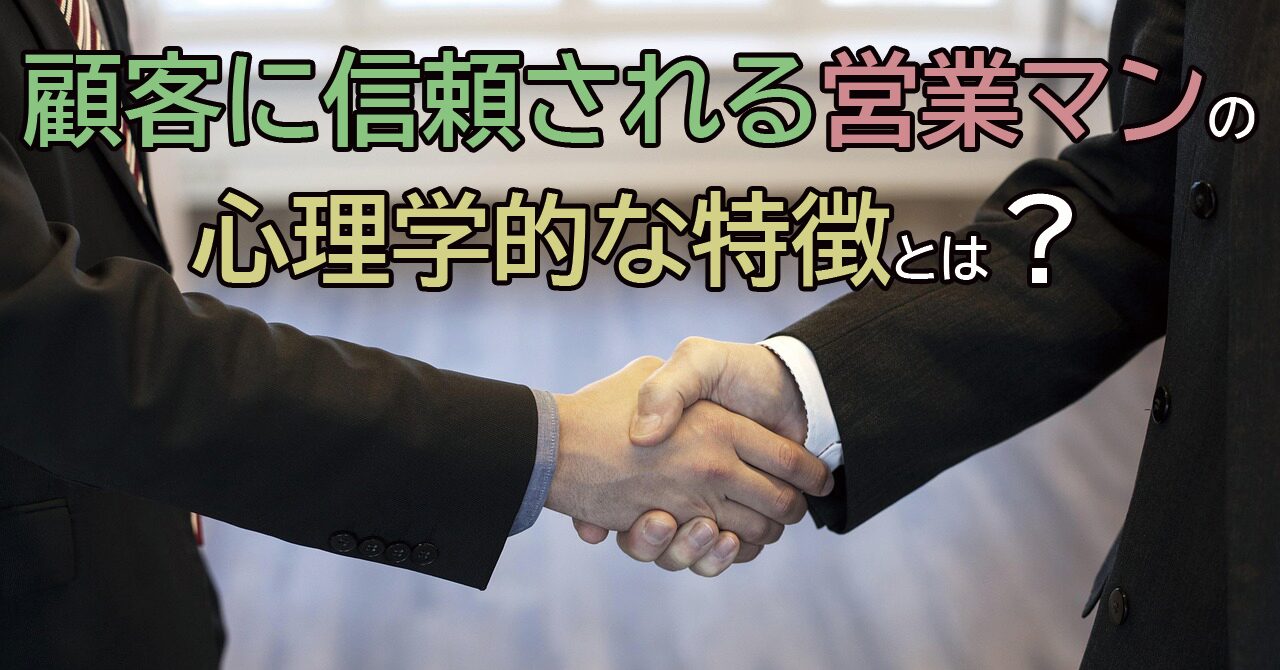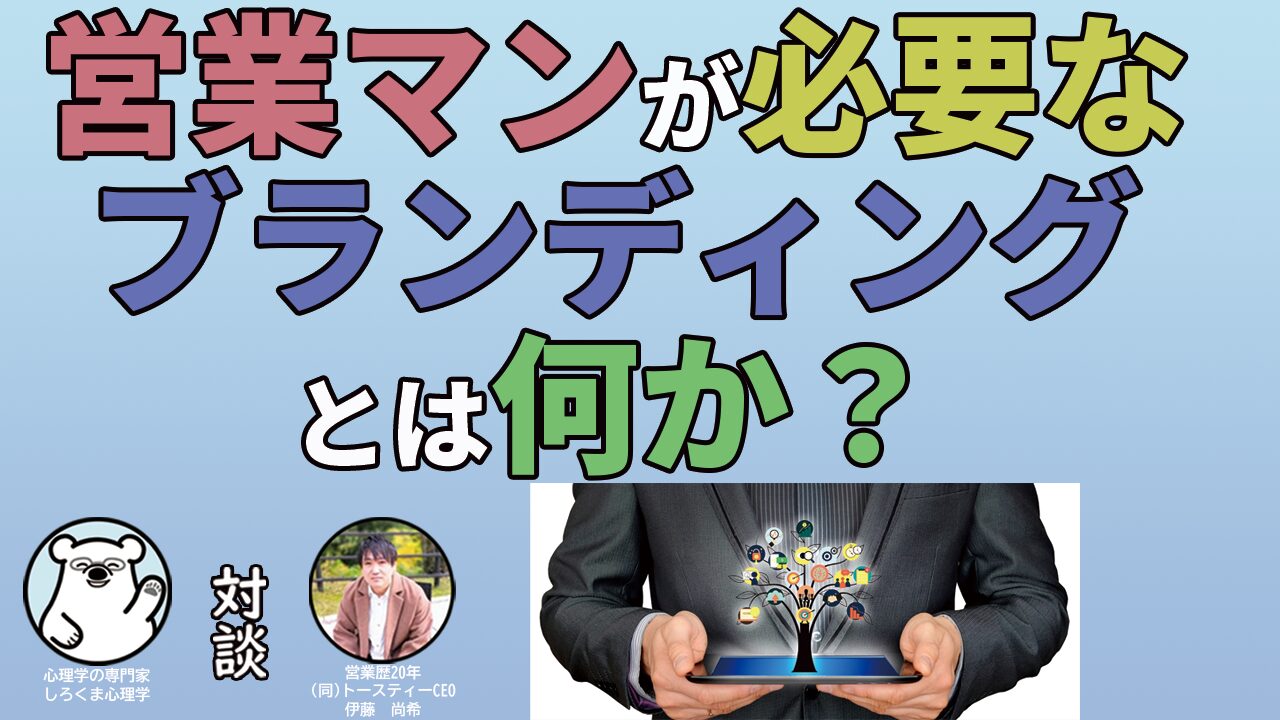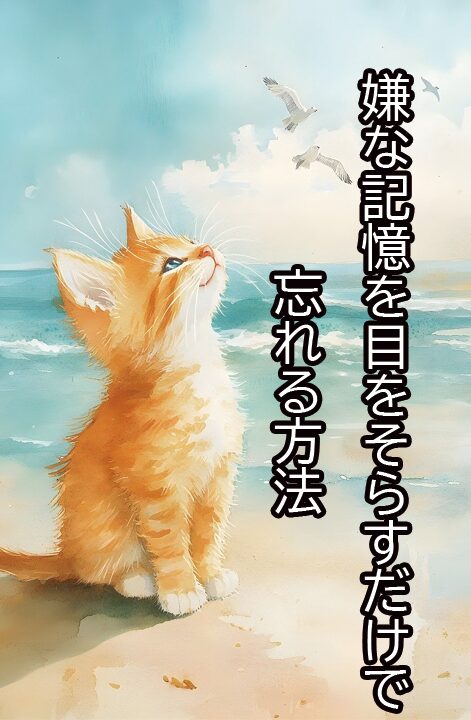ベンヤミン「暴力批判論」後半
今回は、ベンヤミンの有名な論考である「暴力批判論」の後半です。
ちなみに前半部分は「ベンヤミン「暴力批判論」の要約と解説 前半」をクリック。
前半は、「暴力批判論」の理論的な用語確認という序章的な位置づけでした。
軽くまとめると、ベンヤミンは暴力を原理的に、根本的に見直すために、法と正義の目的-手段という関係ではなく、「手段」だけ焦点を置きました。
そして、手段に焦点を置いたところ、実定法的考えと自然法的考えとが見いだされ、手段を問う実定法的考えに行き着きます。
そして、目的の概念を導入して、実定法の性質から、適法的・歴史的基礎付けのあるものを「法的目的」とし、それがないものを「自然目的」と定義しました。
ここまでが、前半の内容です。ベンヤミンの論考は深くておもしろいのですが、言葉足らずなところがあって苦労しています。
後半は、これらの用語を基に議論が実際の暴力へと展開されます。
結論から言えば、暴力は「法一般と関わっている」ことを主張します。
ではどのように暴力と法が関わっているのか?
本記事では以下のことが学べます。

2. 法と暴力との関係
3. ストライキ権や軍国主義国家の暴力
4. 二種類の暴力について
スポンサーリンク
①法と自然目的との対立
まずベンヤミンは、法的目的と自然目的との関係を考察し、近代ヨーロッパの立法には次のような一般的原則があると言います。
個人の自然目的はすべて、多かれ少なかれ大きな暴力をともなって追求される場合には、法的目的と必然的に衝突することになる。
つまり、法的・歴史的に承認されていない「自然目的」の下で振るわれる暴力は、法的・歴史的に承認された「法的目的」と対立するというのです。
これは、一見難しく思われますが当たり前のことです。
「自然目的」での暴力はある意味何でもありなので、過去の過ちから得た教訓などを基にした「法的目的」と合わないのです。
そのような過去の教訓を脅かすような暴力を「自然目的」の下ではする可能性があるからです。
この原則からさらに、法は個々人が手にしている暴力を、法秩序を揺るがす危険とみなす、という考えが生まれる
ここで出てくる法は、法一般のことですね。
法自体が、暴力をおそれるという感じだと分かりやすいと思われます。
何でもありな行いが法に関係なく行われるので、法の意義を揺るがしかねないのです。
スポンサーリンク
②偉大な犯罪者と暴力の正当化
ここで、具体例として、偉大な犯罪者が登場します。
「偉大な」犯罪者の姿は、たとえ彼の目的が反感を引き起こすものであったとしても、これまでもたびたび民衆のひそかな賛嘆の念を生み出してきた・・・こういったことが可能となるのは、その犯罪者が行為のためではなく、ひとえに暴力のため、その犯罪者の行為によってその存在が証拠だてられている暴力のためである。
つまり、法からはみ出した暴力が、その犯罪者本人の行動自体によって正当化されてしまう。
そういう暴力のことを述べています。
この暴力は、まさに法と関係する暴力です。
なぜなら、法を変えうる暴力だからです。
ようやくここでベンヤミンの述べる「暴力」が登場しました。
では、そのような暴力とはどのような行為があるのか?
具体的にストライキ権をベンヤミンは挙げます。
労働者に保証されたストライキ権というかたちをとる階級闘争のうちに見られる。組織された労働者は、国家と並んで、暴力の権利を認められた、今日ではおそらく唯一の権利主体であろう。
ストライキ権は、法に認められた暴力です。
その後、ストライキ権がどのように認められるに至ったかを詳細にかつ簡潔にベンヤミンは述べています。
その中で、「ある種の権利を行使するときの振る舞いもまた、ある特定の条件のもとでは、やはり暴力である」とさらなる暴力について述べています。
ストライキ権の行使も文脈によっては法を脅かす暴力になるというわけです。
ここのところは、ストライキ権の文章を読んでいただくことをおすすめいたします。
詳細は省きます。
スポンサーリンク
③暴力の定義:法措定的な暴力
そこで、ベンヤミンは重要な暴力の概念を見いだします。
つまり、具体的にいえば、そのような振る舞いが積極的なものである場合、自らに認められた権利を、それを付与した法秩序を打ち倒すために行使するのであれば、その振る舞いは暴力と呼んでも差し支えないだろう
法秩序を揺るがす権利行使が暴力だということです。
ストライキ権の話から、「それによって正義の感情がどれほど傷つけられることがあろうとも、暴力は法的諸関係を打ち立てたり修正したりすることができるのだということを、ストライキは示しているのだ」と結論づけています。
この後にさらに戦争権の話をしますが、割愛します。
そしてまさに、ストライキ権のように、「法的諸関係を打ち立てる」そのような暴力には、「すべて・・・法措定的な性格が備わっている」と言います。
ここがキーポイントのひとつです。
ベンヤミンは、法との関係で問題となる暴力の考察をしていますので、この暴力の「法措定的な」機能はひとつの結論になります。
しかし、ベンヤミンは続けます。法措定的な側面以外の性質もあるというのです。
スポンサーリンク
④暴力の定義:法維持的な暴力
ここで先の戦争権の話から、軍国主義の考察をします。
軍国主義とは、国家の目的のために、手段としての暴力を国民全員が使うように強制することである。
国民が暴力行為を行うことを可能にする国家暴力ですね。
こういった強制の本質的な点は、暴力を、法的目的の手段として用いることにある。
つまり、暴力が法の目的を達成するための手段になるのです。
これは、暴力が法を強めることになります。
軍国主義下では、国家が定めた法に則って暴力が行われます。
このような国家では、暴力が法の力を正当化し強めるのです。
結果、暴力は、法を強めたり維持したりする機能があります。
そして、「暴力の第一の機能が法措定的なものであるとすれば、この第二の機能は法維持的なものと呼んでよいだろう」と結論づけます。
スポンサーリンク
⑤まとめ
最終的に、「暴力はすべて、手段としては、法措定的であるかあるいは法維持的である」としてまとめられています。
以上が、ベンヤミンの述べる法と関連した暴力の二つの側面です。
この後も結構論が展開されているのですが、骨子はこのようなところです。
我々が思い浮かべる、殴る蹴るなどの暴力とは少し離れましたが、国民による「法措定的な暴力」と国家による「法維持的な暴力」との二つを見いだしただけでも相当な功績だと思われます。
ベンヤミンの「暴力批判論」の論考は100ページにも満たないですが、かなり内容の濃い論理展開が繰り広げられています。
短くかつ有意義な文章だと思いますし、なによりこの短い考察が現代暴力論の土台となっています。
読む価値は十分にあると思いますので、暴力について考える方にはおすすめです。
スポンサーリンク